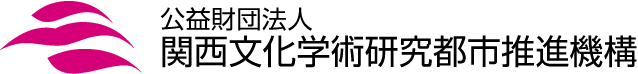開催日:2025年5月30日(金)13:00~14:50 <ハイブリッド開催>
新たな都市創造会議は、"世界の未来への貢献"と"知と文化の創造"をビジョンに掲げて策定した「新たな都市創造プラン」を推進していくため、2016年4月に設置した「けいはんな学研都市」のネットワーク型運営体制です。
第9回となる今年の総会は、6年ぶりの現地開催(オンライン併用)となり、国土交通省をはじめ国の9機関、10自治体、9大学、12研究機関のほか、財界・民間企業・地元まちづくり団体などをあわせて約60名の顧問、委員にご出席を頂きました。冒頭に関西文化学術研究都市推進機構の堀場理事長から、本都市のさらなる成長と新たなビジョンに向けて提言を頂くよう挨拶があり、①本都市の全体的な進捗状況と関係自治体からの近況報告、②イノベーション推進の進捗状況、③けいはんな万博の状況、④現ステージプランの総括と次期ステージプランに向けての報告をもとに、ご出席者からさまざまな意見交換が行われました。
現ステージプランの「新たな都市創造プラン」では、「イノベーションの強化」、「学術研究成果の広域展開」、「交通ネットワークの構築」の課題への取組を推進してきましたが、本総会をもちましてその総括を完了し、「新たな都市創造会議」は最後となりました。そして、その達成度や課題等を踏まえて次期ステージプランの検討につなげていくことが本総会にて確認されました。
<顧問・委員からの主なご意見要旨> ※同義の意見は割愛しています。
1.けいはんな学研都市の近況について
- クラスター開発では、昨年度に狛田東地区の造成工事が完了し、今年度中には南田辺西地区の開発事業に着手する形で進めていく。木津東地区では土地区画整理事業の事業化に向けて関係機関と協議・調整を進めている。
- 学研都市と母都市を結ぶ広域的な交通アクセスや、クラスター間接続などの課題改善に向けて、地域公共交通計画を策定し、将来像と向こう10年間で取り組むべき具体的施策を示した。
- 昨年末の公道を使った自動運転EVバスの走行や、今年2月の複数モビリティの分散協調運行など、多くの住民が観覧されるなか実証実験が行われた。
2.イノベーション推進について
- 地域の特色あるイノベーションを生み出し、社会課題の解決や新たな市場を生み出す観点から、けいはんな学研都市は地域イノベーション拠点として、極めて重要な役割を担っている。
- けいはんな学研都市の環境の中で、イノベーション推進となるような次世代通信ネットワーク技術の実装に向けて取り組んでいきたい。
- AI利用の5Gから宇宙通信、量子暗号通信といった最先端の研究開発を推進し、けいはんな学研都市の研究機関が産学官連携で取り組んでいける政策としても推進していきたい。
- 科学技術立国の実現に向けて科学技術イノベーションの発展を目指し、地域への取り組みが一層重要であり、共創の場形成支援プログラムにおいて、産学官共創拠点の形成を通じたオープンイノベーションを推進している。
3.けいはんな万博の状況について
- けいはんな万博は、その効果をこの地域に波及させるとともにその成果を継承して発展に結びつける取り組みとして極めて重要である。
- 一つのテーマにスタートアップを掲げて様々な取り組みがなされ、スタートアップが次々と生まれ、成長をサポートする拠点の形成に熱心に取り組んでいる。
- けいはんな学研都市の特徴である最先端のサイエンス、テクノロジー、教育と芸術を融合させて魅力を発信したい。
- アバターによる公道パレードや競技会など、国境や研究所の枠を越え、また世代を越えたボーダーレスな取り組みが実感できるようになっている。
- ゲーム技術を使ったゲーミフィケーションを地域のインフラとして展開できないか考えており、アバターチャレンジなどに大きな可能性を見てきた。こういうことを通じて、ポスト万博、次のステージに何らかの貢献ができればと考えている。
4.現ステージプランの総括と次期ステージプランに向けて
- 今年度は次期ステージプランを考えていく非常に大事な節目の年である。
- シームレスな社会を目指し、新たな次の世代に向かったプランを作り、明るい未来を共に描いてまいりたい。
- 南田辺西地区の未整備クラスターを今後フードテック構想拠点に位置づけるように、各クラスターの特色をどう打ち出していくかという視点が必要である。そういった取組を進めていくことで、学研都市全体の強みや特色がより明確になり、文化学術研究都市の立地が進むことにもつながる。
- 公共交通整備が学研都市建設における最大の残課題であるとの認識を共有し、最重要施策として位置付けたい。地域公共交通計画を京都府域だけでなく奈良県域、大阪府域でも策定し、府県やクラスターを繋ぐような道路、公共交通のネットワークの整備を進めていく必要がある。
- 従来型のモビリティや移動の仕組み以外に新しい高齢化社会に適したインフラ整備、文化的な整備も必要である。
- グローバルなスタートアップの創出育成を一つの視点としてイノベーションを推進し、けいはんな学研都市が世界の名だたる拠点に伍する都市となることを期待する。
- 人口や研究論文発表件数、会議数など発展してきているが、定性的で目標やその達成度が見えない。次の目標を立てる時は、ある程度定量的なものがあればいい。
- 素晴らしい研究機関や企業が集積し、ポテンシャルを持っていることは明白だが、さらに欲しいのはこの地域の知名度である。この知名度のさらなる向上がモチベーションを高め、もう一つ大きなポテンシャルアップにつながる。
- 研究所でも若手人材が足りず高齢化現象が起きている。若手研究者を引っ張っていく一つの工夫として近隣の大学とのコラボレーションによる連携講座や研究活動をしている。そのネットワークをさらに広げ、インターンシップを幅広く受け入れて若手の人材育成をしていきたい。
- 大学も若手人材の育成に非常に困っている。人材が減少していくなか、25年先、30年先を見据えてどのような組織を構築していくかが課題となっている。
- 大学は研究機関として産学官連携の協働はもちろん、この地域の活性化において、学生のPBLのフィールドとして重視できるのではないか。
- けいはんな学研都市は筑波と違って文化、歴史があり、非常に広い地域に分散している。これが利点であり欠点でもある。
- 活性化の一つの形として海外から多くの人に来ていただくことがあげられるが、古いまちなかではなかなか難しい面がある。そういう意味で、けいはんな学研都市は一つのモデルとして、非常に多様性のある都市になるのではないか。
5.その他(けいはんな学研都市について)
- 昨年度、税制の特例が延長できたが、この特例が継続できるよう、地元での積極的な制度のPRと活用をお願いしたい。
- 文化財を活用した文化観光の推進や、食文化の魅力発信、地方創生に一層資する取り組みを展開していきたい。平城宮跡など我が国の宝である文化財については、適切に保存して後世に継承するとともに、新たな付加価値を創出して持続可能な活用を推進しなければならない。
- けいはんなの食文化の特徴を活かしたフードテックかつイノベーションを連動させたスタートアップを、海外から呼ぶだけでなく自分たちで作って世界に発信し、けいはんなの知名度を向上させたい。
- 研究活動の成果やこの都市の歴史を記録し保存することも重要である。
- けいはんな学研都市を拠点に選んだのは間違いなかった。人材が豊富で、研究環境や地元の自治体のバックアップ体制が充実している。
以上